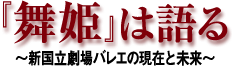次は新国立劇場バレエについて、話を広げてうかがおうかと思います。とりわけ、創作バレエの話など、うかがいたいと思います。
次は新国立劇場バレエについて、話を広げてうかがおうかと思います。とりわけ、創作バレエの話など、うかがいたいと思います。
創作バレエに関しましては、『梵鐘の聲』、『踊れ、喜べ、汝幸いなる魂よ』に続く挑戦となります。創作バレエを多数手掛けられていらっしゃる望月さんに、新国立劇場で新作バレエを作るメリットをうかがいたいんですが、実際作ってみて、こういうところがよかった――ダンサーなり、施設・設備なりについて、よかった点がありましたら、聞かせてください。
 うーん…そんなに他と違っているっていうふうなところは…。まあ、広いスタジオがあるとか、この時間帯はダンサーが拘束できるとかっていうふうなことに関しては、メリットっていうか、ありますけども…。
うーん…そんなに他と違っているっていうふうなところは…。まあ、広いスタジオがあるとか、この時間帯はダンサーが拘束できるとかっていうふうなことに関しては、メリットっていうか、ありますけども…。
新国立だっていうよりも、今回の事に関しては、酒井はなというダンサーと(太田豊太郎役の)白石貴之というダンサーと知り合えたっていうのが、いちばんのメリットだと思ってます。
 設備に関しては、回り舞台を初めて使われるそうですね。
設備に関しては、回り舞台を初めて使われるそうですね。
 はい、そうなんです。長いこと振付師やってて、回り舞台使うの初めてで。回り舞台はね、大変なんですよね、前後とかなんとかが。それで、こういうCDのディスクに白い紙を貼って、これをクルクル手で回しながら、どんだけ回ってるかなって。90°だと思ってやってるのが、180°だったり。「あー、だめだ。これじゃ、ダンサーが全部、真うしろ向いて踊ってる」とか(笑)
はい、そうなんです。長いこと振付師やってて、回り舞台使うの初めてで。回り舞台はね、大変なんですよね、前後とかなんとかが。それで、こういうCDのディスクに白い紙を貼って、これをクルクル手で回しながら、どんだけ回ってるかなって。90°だと思ってやってるのが、180°だったり。「あー、だめだ。これじゃ、ダンサーが全部、真うしろ向いて踊ってる」とか(笑)
 演出の回転させる角度のために、CDのケースとCD使われているとは、とても面白いですね。
演出の回転させる角度のために、CDのケースとCD使われているとは、とても面白いですね。
 ええ。スタッフから特許取れとかって言われまして(笑)
ええ。スタッフから特許取れとかって言われまして(笑)
 中劇場の4面舞台を使われるわけですが、それは他の劇場と使い勝手という点で違いませんか?
中劇場の4面舞台を使われるわけですが、それは他の劇場と使い勝手という点で違いませんか?
 今回は僕の作品だけでなくて、金森君の作品とか石井先生の作品とかがあるから、3人がいちばん舞台をスムーズに使うっていうのが、最低条件としてありますから。
今回は僕の作品だけでなくて、金森君の作品とか石井先生の作品とかがあるから、3人がいちばん舞台をスムーズに使うっていうのが、最低条件としてありますから。
回り舞台ってのは、普段は、普通の舞台の奥にあるんですけれども、それは入れ替えるだけですみますから、スタッフの中でも回り舞台使うことは可能だっていうことなんです。
新国立劇場だから、回り舞台をうれしがって使っているってことではなくて、見てもらったら分かるんですけども、どうしても回り舞台が効果的だっていう場面があって、そのために、それを回り舞台で見せたいがために回り舞台にしてるっていうだけで、子供が新しいおもちゃ与えられたみたいに、喜んでクルクル回してるわけではないんです。
 酒井さんにうかがいたいんですけど、ダンサーの側から見ますと、日本人の振付家で創作バレエを踊るっていうのは、他の、例えばプティパの作品とかを踊るのと違った意識はあるんでしょうか? 別に変わらないんでしょうか?
酒井さんにうかがいたいんですけど、ダンサーの側から見ますと、日本人の振付家で創作バレエを踊るっていうのは、他の、例えばプティパの作品とかを踊るのと違った意識はあるんでしょうか? 別に変わらないんでしょうか?
 意識ですか? プティパは、古典で型がしっかりある中に自分を入れていって、その中で自分を表現するというところがあるんですけれども。振付家の先生と一緒にやるってのは、ゼロから作っていくっていう感じです。
意識ですか? プティパは、古典で型がしっかりある中に自分を入れていって、その中で自分を表現するというところがあるんですけれども。振付家の先生と一緒にやるってのは、ゼロから作っていくっていう感じです。
 ゼロから作っていくのは、ダンサーにとって面白いんでしょうか? それとも、むしろ苦労が多い?
ゼロから作っていくのは、ダンサーにとって面白いんでしょうか? それとも、むしろ苦労が多い?
 私は、とても面白いです。
私は、とても面白いです。
 望月さんは、役の踊り方の解釈は、ダンサーにまかせていらっしゃるという話がありましたけど、古典作品を踊るより自由度が大きいところも、ダンサーにとっては面白いところですか?
望月さんは、役の踊り方の解釈は、ダンサーにまかせていらっしゃるという話がありましたけど、古典作品を踊るより自由度が大きいところも、ダンサーにとっては面白いところですか?
 そうです。とても、それは。
そうです。とても、それは。
毎日、いろんな感じ方が出て、表現を見てもらって、よかったり、悪かったりっていうふうなのを見ていただけるし。
コンスタントにテクニックを出すのと違って、感情を出していく見せ方っていうのは、毎日、毎回違って…。リハーサルが、発見があって毎回新鮮です。
 新国立劇場バレエの前に、牧阿佐美バレヱ団で踊ってらっしゃって――今、芸術監督、牧阿佐美さんがやってらっしゃっるわけですが――その両方のあいだに、ダンサーから見て違いはありますか?
新国立劇場バレエの前に、牧阿佐美バレヱ団で踊ってらっしゃって――今、芸術監督、牧阿佐美さんがやってらっしゃっるわけですが――その両方のあいだに、ダンサーから見て違いはありますか?
 リハーサルするお部屋とパフォーマンスをする劇場が同じっていう、自分の劇場があるってことでしょうか。
リハーサルするお部屋とパフォーマンスをする劇場が同じっていう、自分の劇場があるってことでしょうか。
 ちょっと細かい話かもしれませんが、メソッドについて、牧阿佐美さんのところでされていたメソッドと新国立のレッスンのメソッドで、違いはなかったですか?
ちょっと細かい話かもしれませんが、メソッドについて、牧阿佐美さんのところでされていたメソッドと新国立のレッスンのメソッドで、違いはなかったですか?
 最初のころは、ワガノワのロシアの方がいらしていて(牧とは)違ったので――牧では割りとロイヤル・スタイルの方なので――ちょっと身体的に大変でしたけど、でもとてもいい勉強になりました。
最初のころは、ワガノワのロシアの方がいらしていて(牧とは)違ったので――牧では割りとロイヤル・スタイルの方なので――ちょっと身体的に大変でしたけど、でもとてもいい勉強になりました。
 今はワガノワから、またロイヤル・スタイルの方に…
今はワガノワから、またロイヤル・スタイルの方に…
 はい。ロイヤルの『シンデレラ』をやりました。
はい。ロイヤルの『シンデレラ』をやりました。
 レッスンの仕方ってのは変わったんですか?
レッスンの仕方ってのは変わったんですか?
 はい、変わりました、その時は。だから、その演目によってレッスンが変わります。
はい、変わりました、その時は。だから、その演目によってレッスンが変わります。
 今は、J-バレエに向けてのレッスンのスタイルってのは、あるんですか?
今は、J-バレエに向けてのレッスンのスタイルってのは、あるんですか?
 J-バレエみたいな時は、ミストレスの小林(紀子)先生、大原(永子)先生にレッスンをしていただいて、特にメソッド的なものは…。
J-バレエみたいな時は、ミストレスの小林(紀子)先生、大原(永子)先生にレッスンをしていただいて、特にメソッド的なものは…。